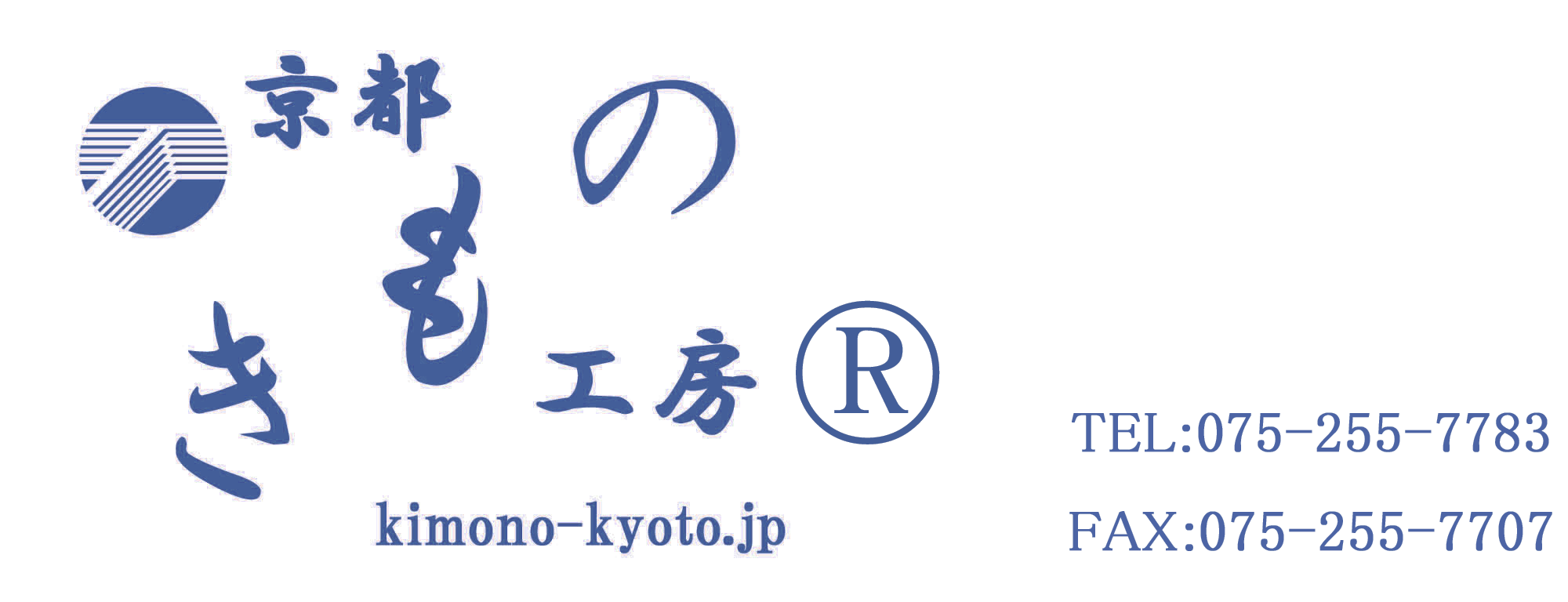銘仙とは、先染めの平織りの絹織物です。銘仙の源流は、屑繭や玉繭からとった太い糸を緯(よこ)糸に用いた丈夫な縞織物(太織)で、秩父周辺の養蚕地帯の人々の自家用の着物でした。
それが明治時代の縞柄の流行に乗って関東で着られるようになり(「縞銘仙」)、大正期には絣模様を織り出した「絣銘仙」が流行し、伊勢崎、群馬県桐生、埼玉県秩父、栃木県足利、東京都八王子等北・西関東を中心に生産されるようになりました。
大正の中頃に「解し織/ほぐしおり」の技法発明され銘仙の生産が一新される事になります。
経糸を並べてずれないように仮織りし、模様を捺染し、仮織の緯糸を抜いて解しながら、再び緯糸を通して本織するこの技法によって、たくさんの色を用いた複雑な柄の着尺(きもの生地)を効率よく生産できるようになりました。
この頃から伝統的な天然染料に代わって染色効率が抜群によく色の彩度が高い人工染料が用いられるようになりました。
技術革新を背景に、大正末期?昭和初期のモダン文化の流行に乗り欧米の洋服地デザインの影響を受け大胆でハイカラ、色鮮やかな「模様銘仙」が大流行します。模様銘仙のデザインは、着物でありながら、ヨーロッパアートの潮流の影響を受け、大正期の模様銘仙には曲線的なアールヌーボー、昭和には直線的で幾何学的なアールデコ調が出現します。
昭和初期、銘仙全盛期の秩父では、デザインを東京の美術学校で洋画を専攻している学生に委嘱したり、来日したフランスのデザイナーと交流したり、ドイツから輸入した染料を使ったりしていたそうです。地元の職人さんも、そうした最新のモダンデザインを着尺に乗せることに職人的プライドを感じて、さまざまな技術的チャレンジを繰り返しました。
現在アンティーク着物として残る銘仙の色柄の中にまるで油絵を思わせるものやヨーロッパの同時代のデザインに比べても遜色のないものがあるのは、こうした新しい発想と努力の結果でした。
また、工場で大量生産される安価な銘仙の出現によって、それまでは木綿しか着られなかった庶民の女性までが絹の着物に袖を通すことができるようになりました。
こうして大正後期?昭和期初期に、銘仙は、東京を中心に中産階級の普段着、庶民のおしゃれ着、カフェの女給の仕事着として地位を確立しました。
銘仙は、戦後の、繊維製品の統制が解除された昭和20年代後半から30年代前半(1950?1960)にも、伊勢崎を中心に生産され、アメリカの洋服地を模倣した大柄で華やかなデザインのものが流行しましたが、その繁栄は短く、昭和32年(1957)にウール着尺が発明されてブームになると、その地位を取って替わられ、着物が普段着のではなくなった昭和40年代(1965?)以降はほとんど姿を消してしまいました。
今、アンティーク着物として私たちが手に取る銘仙は、ほとんど「模様銘仙」か「絣銘仙」で、
昭和初期の着物は70年前後、戦後の着物も約40年昔の着物ということになります。
初期のものほど緯糸の節が目立ち「ぶつぶつした感じ/ネップと言います」、時代経過とともに次第に糸の節が目立たず滑らかなものが多くなります。昭和の大量生産品は滑らかで光沢のあるものがほとんどですが、緯糸に人絹を用いた水に弱く強度不足(張力に弱い)の粗悪品も数多く出回ったので注意が必要です。